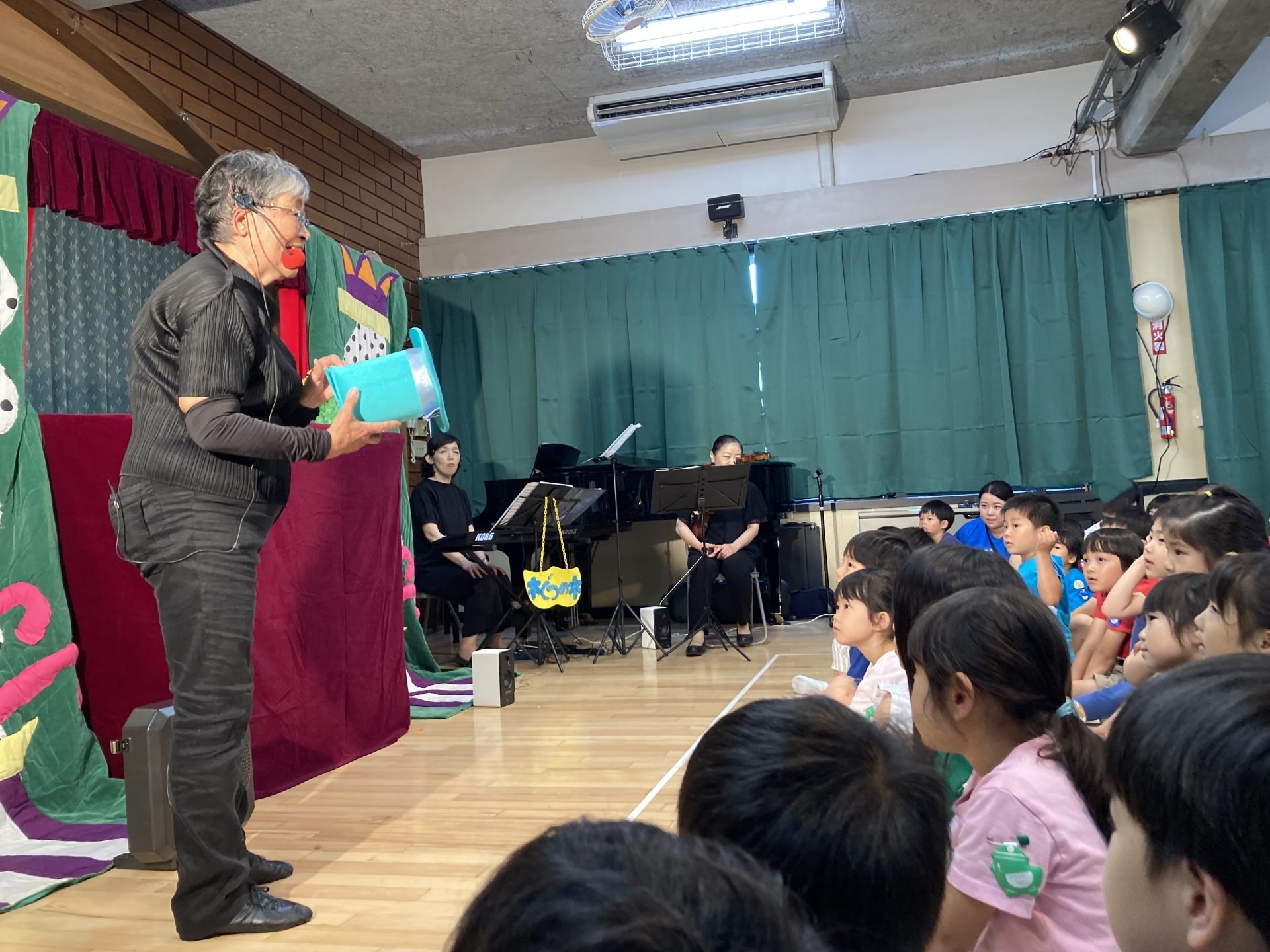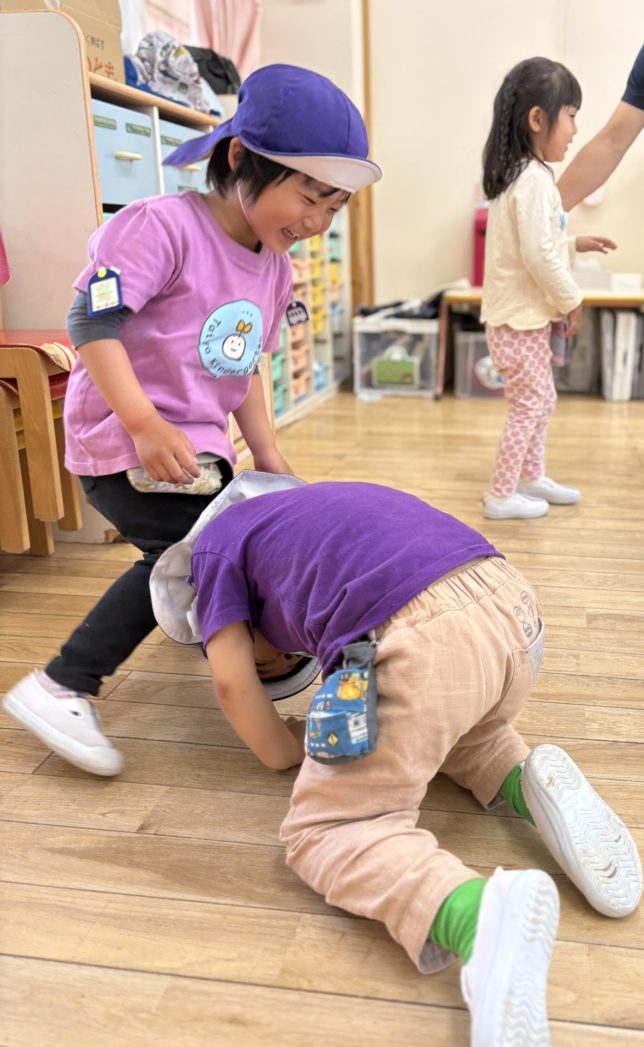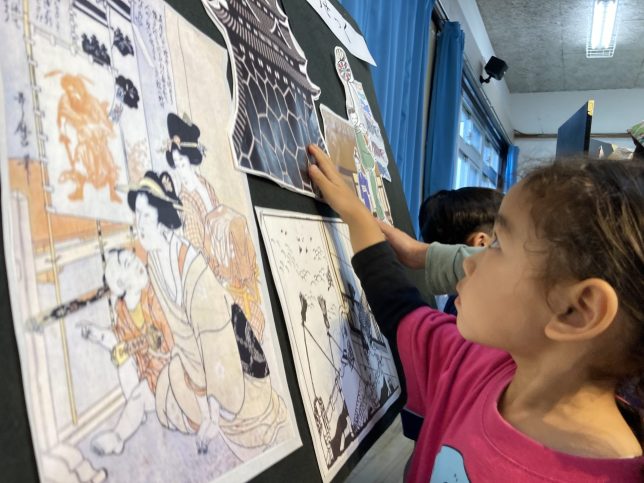今年も、土の感触や匂いを感じながら、肥料と一緒に混ぜ合わせ、苗から野菜(ミニトマト・なす)を育てました。
いよいよ夏になり、収穫できるほど大きく成長したので、「ミニトマトとなすのミートソースペンネ」を作りました。 早速エプロンを身につけ、胸を躍らせる子ども達。教師と一緒に包丁にも挑戦しました✨包丁を持つ子ども達は真剣な眼差し。できあがって食べてみると、「甘くておいしい〜!」と何度もおかわりする姿や、「包丁使えて嬉しかった」「(トマトやナスが)あんまり好きじゃなかったけど、ちょっと食べられたよ!」などと初めての体験に対する喜びや挑戦できたことへの嬉しさを話す姿が見られました。 自分達で育てた野菜の味は、格別だったようです☺️✨